
【小学生への読み聞かせ】子どもの反応の変化とは?(元小学校教員の実感をシェア)
当協会は、「声のぬくもりで子どもの生きる力を育む」
読み聞かせの普及に取り組んでいます
その必要性を感じるのは、子どもたちの反応の変化があります
教育現場で、長年子どもたちと接している
保育士、幼稚園教諭の認定講師からは
「待てない」「言葉が少ない」現状があるとの事です
そして現在、「絵本・読み聞かせスペシャリスト認定講座」を
オンラインで受講中の元小学校教員Kさんは
「国語の授業や言語発達に力を入れても
小学生からでは遅いと感じています」
「0歳から入学前までの読書体験が大事です」と
実感されています
その背景には、動画やショート動画、AIの音声に
慣れている子どもたちの現状です
・盛り上がる場面が終わると、最後のページを聞いていない
・裏表紙の余韻を楽しむことなく、「次の絵本は?」と急かす
・ある絵本で、猫が子猫に絵本を読んでいる場面では
「猫は、絵本を読めないよ」と言い出す
その変化は、15年前ぐらいから変わってきたそうです

このように、見たり聞いたりした事以外は
「ありえないない」と感じる想像力が乏しい状況に
考えさせられてしまいます
授業の変化にも、大変驚きました
今まで、声優さんの音声であったのが、AIとのことですし
計算も黒板に書かずに、画面に表示されるそうです
そのこともあってなのか、すぐに答えを知りたがるそうです
日々の生活では、◯でも×でもない答えがありますし
その過程を考え、取り組むことは
人生を生き抜く力に通じると思うのですが
あなたは、どのように感じられますか?
子どもたちの変化を分かりやすくまとめると
お話の世界を電車で旅している時に、次の駅のアナウンスが終わって
いよいよ駅に着くというのが、最後のページだとしたら?
子どもたちはアナウンスを聞いた直後(絵本の盛り上がる場面)に
反対ホームの電車に乗って、発車するのを待っている状態だと言えるのです
「待つ」ことは、コミュニケーションでも
大切な場面があります
例えば、お友達が、なかなか自分の思いを言えない時
「待つ」ことができる子は、「大丈夫だよ。ゆっくりで良いよ」と
優しい言葉を掛けて、そのお友達が言葉を発しやすくなるように
安心させてあげて待っている一方で
すぐに答えを知りたくて待てない子は
「なんでだまっているの?早く言ってよ。
言ってくれなきゃ分からないよ」と
追いつめてしまうかもしれません
このまま大きくなって、大人になった時を想像すると
「思いやり」という言葉が存在しないのではと思うほど
元小学校教員Kさんから伺い、とても考えさせられました
だからこそ、子どもたちの心と言葉を豊かに育む
絵本の読み聞かせの読書体験が大事だと再認識しています
それでも、絵本を読むだけでは十分ではありません
子どもの想像力が膨らみ、感情表現豊かな言葉に繋がる
読み聞かせ方法の実践が、大変重要です
当協会の読み聞かせメソッドは
全国図書館協議会選定図書に選ばれていますので
オンラインで習得しませんか?
あなたの読み聞かせが、子どもたちの成長を
豊かに育む読み聞かせ変わるメソッドです

あなたの読み聞かせでは
子どもたちの反応はいかがでしょうか?
「ようやく腑に落ちました」と分かりやすさが好評の
読み聞かせメソッドを深く学んでみたい方は
良かったら、下記のリンク先をご覧下さいませ🔻
〜現在、受付中の講座〜
絵本とふれあい親子愛を深める
初めての読み聞かせ講座 → こちら
子どもの心を豊かに育む読み聞かせに変わる(受講証明書)
また読んで欲しくなる読み聞かせセミナー → こちら
【絵本・読み聞かせスペシャリスト認定講座】→ 短期・こちら
オンラインで読み聞かせの資格が取得できます
・無料の個別相談では、ご自分の声質を活かせる読み聞かせ
【声質に合う絵本の診断】が大好評です→ 声質診断について
読み聞かせについて配信しています
⇩良かったら下記から登録できます⇩
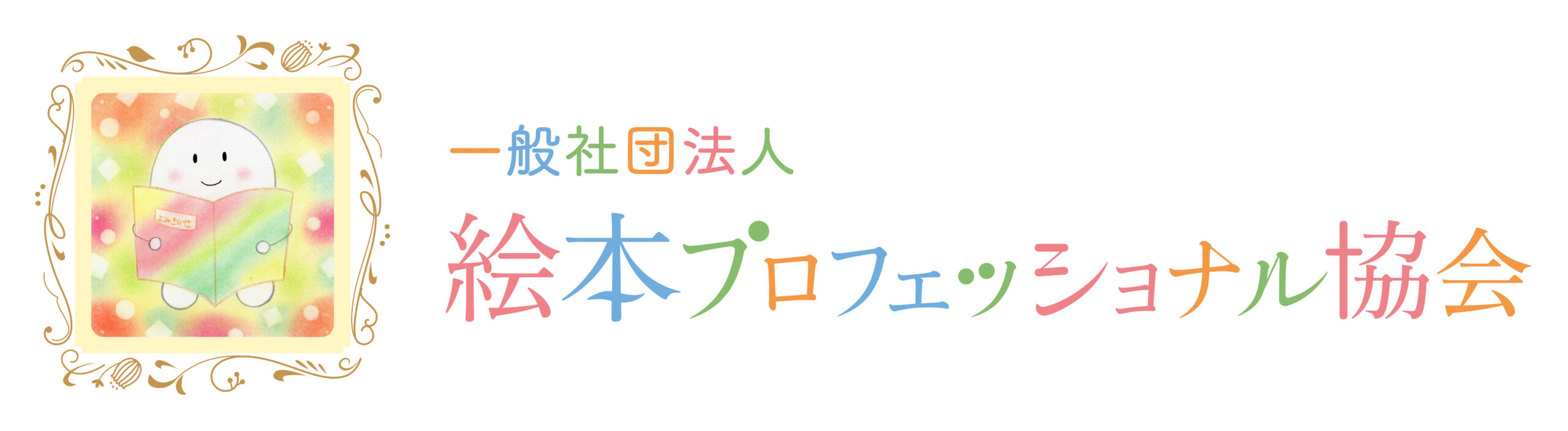






この記事へのコメントはありません。